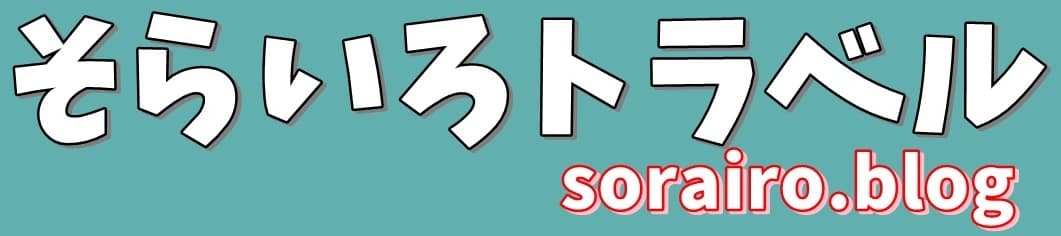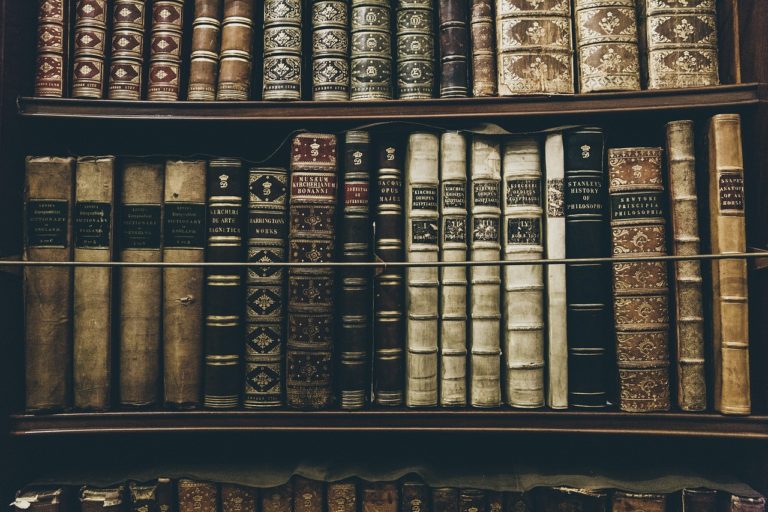「機会」は平等に与えられていない。
裕福な家庭に生まれた者が全員成功者となるわけではないが、潤沢な教育資金によって海外留学などの経験を積み、そこで得た知見や人脈を活かして起業したり、自身の思うがまま「やりがい」を追求し、周囲からも尊敬され、恋愛や結婚をごく自然な幸福だと、豊かな人生の選択肢が用意されている。
一方、自由に学ぶ機会も限られた家庭環境(実家が太くない)で、はるかに強い苦労(苦悩)を経験しても、社会が求める価値(経済効果・影響力)が低ければその努力は正当評価されず、恋愛や結婚といったごく普通の幸せ(平等な機会)を得るためには、やりがい・生きがいといった人生の本懐、つまり「本質的な生」を犠牲にしなければならないというジレンマに直面してしまう。
母は幼少期、住む家もなく、一時期まともに小学校にさえ通う事も出来ず、父は食べるものにも困り、親に手を引かれ入水寸前まで経験したという。
そんな、その時代にしても特に貧しい家庭で育った両親の下で、教育資金も乏しく、海外留学なんて夢のまた夢、「やりがい」で職を自由に選択することなどできるはずもなく、中卒で新聞配達とコンビニを掛け持ちし、果ては最も過酷な重労働の一つと言っても過言ではないビル解体を小柄で経験した。
これが「持たざる側」にとっての真実だが、このままの意識では「妬み嫉み」という感情に支配され続け、ますます「負のスパイラル」に陥ってしまう。
当然、恵まれてない中から努力で成功を勝ち取った人(芸能人やスポーツ選手など)もいるが、それこそ優遇者よりもはるかに高い才能と幸運を必要とし、圧倒的才能などあろうはずもない平凡な不遇側では、再現性のない「奇跡」として遠く眺めることしかできない。
これまで「人生観」(カテゴリー)で、不平等や社会観を長々語ってきたけれど、この卑屈と負の感情の根源が、最終的な目標(価値提供)を阻害してしまうので、その全てのアンサーとして、社会の欺瞞や不平等に対する被害者意識から脱し、運も才能も無い私のような凡庸な「持たざる側」でも実践可能な主体的に生きるための「解」を書き残そうと思う。
序章:労働の美徳の欺瞞
私の両親はその時代にしても特に貧しい幼少時代を生きており、そこで培われた根性が良くも悪くも、どんなブラックだろうと必死に耐えるという資本主義にとって最も都合のいい「プロレタリア根性論(≒労働の美徳)」を叩き込まれてしまう。
それで報われるならまだしも、父は長年勤めた会社に負債の責任を負わされ、半ば強制退職で退職金を没収され、挙句の果てに大病を患い若くして亡くなってしまった。当然、入院費が足りないので、その不足分は私が補った。
そんな親の下で育った私は、どうしても「社会が嘘をついてる」と感じてしまうのだけれど、投資家・経営者(優遇側)は、お金の為に働きたい人に”自分の資金から給料を出している”のは事実であり「そうなるまで頑張れ」と言われていないのは間違いがない。だから福利がある。
少なくとも社会はそういう体裁(建前)のもとで回ってる。
そして、社会は平等ではないのは事実なのだけれど、そもそもお金とは労働の対価ではなく「社会貢献の対価」であり、努力や苦労(苦悩)の対価ではない。
なので、彼ら(優遇側)が、C卒で新聞配達したりビル解体という過酷な労働を経験する事もなく、”普通に”留学して人脈や経験などの有利な条件を手に入れ、”普通に”人生を共にするパートナーを得られて当然の事だと幸福な人生を享受できるとしても、彼ら(優遇側)が評価されるのは「社会に役立っているから(与えているから)」という事実がある。
しかし「持たざる側」でも人並みに恋愛して結婚したいのなら、最初から得ることができる「労働」という一見平等に見える「機会」も与えられてるけれど、この「平等な機会(買う自由)」を得るためには、やりがい・生きがいといった、より「本質的な生」を犠牲にしなければならないという本末転倒な状況になってしまう。
つまり恋愛や結婚などといった幸福や贅沢を「誰もが自由に得られるという建前」こそが社会の欺瞞であり、その実態は不平等な社会構造の上に成り立っている。
メディアの大半は「普通に消費する事」を、そのためには「普通に働く事」を肯定し、それが幸福への道だと錯覚させる。だからそれが普通なんだと、誰でも得ていいのだと勘違いして、ますます資本主義主導の消費社会に搾取されてしまう。
この指摘は、普通に努力をして普通を得られる人(つまり高校・大学を卒業し、恋愛してパートナーを見つけることができる人や、親が不当な目に遭っていない人)には理解しがたい事だと思う。けれども私の家庭のように資本主義の建前と実態の乖離を目の当たりにした側にとって、これは切実な問題だった。
なので、先に幸福(つまり恋愛したり結婚したり)を得るために働くのなら、それは各人の自由だけれども、自己の尊厳の為に生きるためには、彼ら「優遇側」が普通に得るそれらを絶ってでも、先に「原資」を得る必要があるという「解」に至った。
一章:真実を突く哲学者と言葉巧みな経営者
多くの人は、哲学者の真実を突くキツイ言葉より、耳障りのいい言葉に耳を傾けてしまう。
古代ローマの哲学者セネカは著書『生の短さについて』の中で、「誰かに命令されたことを一生懸命やっている人生は、真に生きているとは言えない」(超訳)と表現していました。
これを現代社会に置き換えると、「やりがいを感じない仕事で、収入のために生きる人生は、真に生きているとは言えない」と解釈できる。しかしこう言われて、良い感情を抱く人は少ないでしょう。

ルキウス・アンナエウス・セネカ 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
 |
生の短さについて 他二篇 (岩波文庫) [ ルキウス・アンナエウス・セネカ ] 価格:990円 |
一方、投資家のロバート・キヨサキは、著書『金持ち父さんのキャッシュフロー・クワドラント』で、「人の行動原理は恐怖であり、その恐怖を和らげるために福利厚生を求めて働く人と、自由のために働く人がいる」(意訳)と述べていた。
これは、セネカの言葉と本質的に同じことを別の角度から指摘しているだけのように見える。
しかし、「あなたは福利のために、そのやりたくもない仕事をしているのでしょう?」と直接的に問えば、多くの人から反発を招くのは明白。
だから、経営者たちは「君のおかげで会社の売上が上がる」といった、耳障りの良い言葉に置き換える事で、労働者の意欲を引き出している。
けれども、これで”本当に得ている”のは経営者、及び、投資家であることは誰しもがわかる所。
この事実をキヨサキ氏も理解しているからこそ、著書で「本当に幸せになりたかったら、投資家(及び資産家)になるしかない」と、ストレートに表現している。
*ちなみにこのロバートキヨサキ氏は上記著書で「資本を得るまで9年間車で寝泊まりした」というようなことが書かれていた。

ロバート・トオル・キヨサキ 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
 |
金持ち父さんのキャッシュフロー・クワドラント改訂版 経済的自由があなたのものになる [ ロバート・T.キヨサキ ] 価格:2,090円 |
なれるかどうかは別として、投資家は「お金でお金の問題を解決」するから、人生の時間をやりたいことに自由に使う事ができる。(遊びでも労働でも、ボランティアでも)
しかし、福利厚生に生きる方法(つまり労働者)は、労働の対価としてお金を得るため、その仕事が好きかどうかなど関係なく働き続けなければならなくなる。
私の父のように真面目に会社に勤めた挙句、会社の損失の肩代わりさせられ、不当解雇で退職金も没収され、、挙句、若くしてガンで亡くなるような事になるとしても、途中で辞めるという選択肢は事実上なくなる。これが”普通程度の家庭”に生まれた殆どの人の生き方になってしまう。
もちろん、その生き方にも福利がある。
しかし、そこで得られる福利は、失業した際に、(『定年まで生涯仕事に行く』という契約のもとで受け取れる)”失業手当”や、働き続ける限りにおいて”病気の検査”が受けられることであり、そもそも人生半ばで病気にならない保障もなければ、良き伴侶に出会える保障もなく、仮に無事定年を迎えられても保障されるのは最低限の生活であり、”幸せそのもの”というわけではない。
 |
価格:726円 |
更には、年金やその他充実した福利厚生(社会システム)に頼れば頼るほど*税金や社会保険料は上昇していき、結果として長い年月をかけて多少給料が上がっても、物価なども共に上ってしまい、一向に生活が良くならないのはそれに依存するからという矛盾を産んでしまう。(*少子化の上、景気も良くないのに、物価だけは上がっていくのだから)
要するに、資本主義の基本的な構造としてインフレに向かうように設計されてるので、時間経過による給料アップはインフレにより相殺されてしまう。
なので、労働者でも順風満帆に人生を送れればいいが、「労働だから正しい」と選んでしまった場合、私の父のように人生半ばで”末期ガン宣告”のような、想定外の悪い事が起きたら「そんなはずじゃなかった」と後悔に繋がっていくのは間違いない。
結局それは、生きる上で「自由の為に生きるのと、福利厚生に生きるのはどちらが良いか?」という問題に対して、明らかに「自由の為に生きる(自由を得る為)方が良い」と導き出せる(多くの哲学者が認める)のだが、上述ロバート・キヨサキが言うように、将来に対しての漠然とした恐怖感により「労働(人の会社で働く)しかない」という選択に偏ってしまう。
それを資本を持っている経営者たちは、福利厚生を得たい人たち(要するに労働者)を給料で雇うという資本主義で認められた”合法な”方法を用いて自身の幸福を確保している。
一応語弊の無いように補足しておくと、起業家・経営者が全員悪質だと言ってるわけではないが、仮にその起業家が「社会の課題を解決したい」「新しい価値を創造したい」といった強い使命感を持って事業を立ち上げていたとしても、そこで雇われるのは(資本を)持たざる家庭の労働者だという事実がある。
そして、その事実を多くの「見識者・哲学者」たちが*批判するのだけれど、実際に労働者に給料を出しているのは投資家・経営者だという事実があるので、彼らを「悪質だ」というには矛盾が生じてしまう。
*マルクス資本論でいう所の「労働疎外」がまさにこれに当たる。
福利厚生に生きた結果
セネカの指摘した「自主的でない生き方は真に生きてはいない」といった厳しい表現は、当人が「それで良い」と思ってやっているのだから、殆どの人が「余計なお世話」と感じるかもしれない。
しかし一方で、多くの末期ガン患者を看取ってきた医者が、「彼らの最期に言う言葉の多くが『もっと自分らしく生きればよかった』だ」(ソースは忘れました)と語っていたという話は、この言葉の真実性を裏付けているように思える。
典型的な高度経済成長時代の会社人間だった私の父も、ガンの闘病中に日記をつけてましたが、その内容はシンプルに「もっと生きたい」という人生への深い後悔でした。
生前の父は、特別良い父と言うわけでもないですが、仕事は生真面目に取り組むタイプで、一部上場企業で晩年それなりの役職(恐らく「平取」)にまで出世しており、父のお葬式に役所の”お偉いさん”なども参列していました。
亡くなった後にどれだけ「いい人だった」と言われようが、病気から助けてくれるわけではなく、もっと言うならば、どれだけ粗暴で口が悪かろうとも、病気を治してくれる人の方が有益で価値のある人。
ただ、世界はマンガでないので、当然そんな人はいない。というより、そんな人が存在しない真実の世界だからこそ、現状を戒めるきつい言葉を”先にかけてくれる哲学者”こそ本来価値のある人のように思える。
その価値に気づかないと、彼ら(資本家)の評価のためにずっと競争させられ続け、やりがいなどなく、福利(幸福)の為のはずなのに、義務感で出世する(=生きる)事になってしまう。
結局、私の父もまた、ロバートキヨサキの言う、「福利厚生の為に働く人」であり、セネカのいう”生きてない人”だったという事。それを末期宣告を受けた後に理解しても「後の祭り」になってしまう。(どれだけ悔しかろうとも)
なので、もし”仕事が好きではない(本当に嫌だ)”とまで思うのならば、”福利”が成立しておらず、『福利を与える経営者側』か『「この会社で働きたい」といった労働者側』のどちらか(もしくはどちらとも)が嘘をついてるという構造的なジレンマが生じてしまう。
二章:「社会欺瞞の正体」哲学者も経営者も同じことを言っている
実のところ哲学者と経営者(及び投資家)は、人間の行動原理について同じことを理解しながら、真逆の方向でそれを実践しているだけのように見える。
経営者は、『今月の売り上げ』というノルマを与え、達成による一時の高揚感と”金一封”という報酬を与えている。
それで喜んでいるのは、紛れもなく貰う側の自分自身(労働者側)であり、その金一封で欲しいものを得るのもまた自分自身(労働者側)だ。
つまり、労働者は生涯にわたって「与えられる側」として生活するのだが、そもそもそれを投資家や経営者が頼んだわけではなく、どうあれ自分自身で選んだことになる。
そこで得られるのは一定の給料や休日、保険などであり、それがまさに”福利”となっている。
幸福と利益。希望どおりになって生活などが落ち着くようにすることと、その人のためになること。
引用:コトバンク
しかし、この生き方を「鳥篭の鳥」で例えるなら、一番きれいに囀(さえず)れば丁重に扱われ、より多くの餌を与えてもらえるが、それはまさに運と競争の世界であり、囀れなくなれば価値もなくなり見捨てられてしまう。(事実、定年後に再雇用等でそのまま同じ内容で働き続けても、給料は下げられる。)
なので、生まれ持つ容姿や才能、実家の太さ、労働力で勝ちうる体格などの「運」に恵まれなかった場合、それ(労働そのもの)に生きがいを感じないのならば、給料や役職に生きても、将来幸福に感じるかは保証されているわけではなく、各人の問題になる。
投資家たちが『福利厚生の為に生きなさい』と言ったわけではなく、自分自身が『福利厚生に生きよう』と選択したという事実。そして、その福利(要するに給料)を実際に与えているのは資本家・投資家(経営者)であるという事実。
しかし、一般労働階級の家(つまりプロレタリア)に生まれた多くの人は、既存の学校教育の中で「食べるため(生きるため)に”人の会社で働く道”」しか無いかのように仕向けられてるので、その真偽を自ら疑わなければ、そこから抜け出すのは極めて困難になってしまう。
哲学者はその構造的な問題を指摘するが、投資家・経営者たちは「(面接等で)あなたが働きたいんでしょう?」と、”お給料で雇う”という(合法的な)結論を導き出している。
つまり、経営者たちが使う『君のおかげで社が潤う』等の言葉は、哲学者の『その生き方は愚か』と同じことを真逆に利用しているだけであり、彼ら経営者たちは労働の先に幸福までを約束しているわけではない。
だから、哲学者たちの言葉こそ聞くべきだと感じるけれど、大衆自らが雇われたい・出世したい、つまり「もっと給料が欲しい」と言っているのも事実であり、実際に福利(給料)を与えている経営者・投資家たちは労働者のその願いに応えており、それを選んだのは自分自身だという事になってしまう。
恐らくこれが、社会の煙に巻かれたように感じる欺瞞の正体なのではないかと思える。
三章:欲すればまず…
これは、”宗の教え”的なものではなく、結果論として「欲すれば与えるしかない」という事実を知る必要がある。
多くの人は、得た給料を個人的な趣味や贅沢に使っている。当然それは個々の自由であり全く悪い事じゃない。
けれども、結果論として経済的成功者(経営者・投資家)は、そのお金を自分の物欲などの贅沢にではなく、人に与える事で労働者より得る事に成功している。という事実がある。
つまり、”給料を貰う人(労働者)”より、”給料をあげる人(経営者&投資家)”の方が成功者になっているという事実をまず知らなければ、いつまでも”貰う側”から抜け出せなくなる。
とはいえ、一概に労働をダメだと言ってるわけではなく、個々の得手不得手や幸福の形に依存するので、(普通とされる)人生の中で良きパートナーと出会い「平凡という最高」が得られるのならば、福利に生きる人生にも幸福はある。
それに、給料に関しても、(力でも知識でも)労働力があれば、元グーグル社員のように労働者として退職金9000万ドル(約100億円以上)という”最大限の福利”もありえる。
ただ、報酬という点だけを見ると、起業で発揮したジョブスは200億ドル(約2兆円以上)もの資産を残し、投資という方法で社会イノベーションに寄与したバフェットは約100兆円というケタ違いな資産を得ている。
しかし最も重要なのは、それら全てはお金の価値ではなく(その時代の経済効果の影響を受けるという前提で)社会貢献の価値(地位=ステータス)が金額として表れているだけであり、彼らは全て自らの力(や資金)を人に与えて成功しているという事実を見落としてはいけない。
だからこそ、”持たざる側”であるなら、まず先に自分が得ようと思うのではなく、”欲すればこそ与える”しかない。という事。
好きな事を仕事にする人
スティーブ・ジョブスをはじめ、多くの成功者が口にすることだが、世界屈指の経済的成功者たちも「好きな事を仕事に」と言ってるのだから、経済的成功者はウソをついているのではなく、すなわちこれは、”自身で判断したもの”と言わざるを得ず、「好きでもない仕事でもどうしてもやらなければならない理由」は福利を対価とした先に束縛されるもののように思う。
それに、社会では(特に学校では)不向きな事を頑張ることを美徳としている風潮があるが、それが真理ならば、『碁打ちは野球を、野球選手は囲碁をやるべきだ』という理屈が通ってしまう。
しかしながら、それは考えずとも分かるとおり、”明らかにムダ”であり、やはり自分の中で一番得意な事・好きな事(人と比べてではなく)のほうが、自分のためにも社会全般のためにも大きな成果が出るのは間違いない。(自問自答:多分これは「功利主義」的考えなのかもしれない。)
なので『好きな事をする』は絶対に必要な部分であり、ただしそれは「利己的な好き放題」ではなく、「社会に良い価値を与える事が大前提」だという事は忘れてはいけない。
四章:「買う自由」と「買わない自由」
前述の通り、評価されるには「与えるしかない」のだが、しかし「持たざる側なのに、どうやってその資金を捻出したらいいのか?」という矛盾が生じてしまう。
その方法は単純で、出来る限り贅沢を慎むだけ。なのだが、資本主義の構造上、生産と消費の循環によって成り立っているため、消費を肯定する仕組みになっており、SNSやYouTubeなど、何を見ても物欲が刺激されてしまい、その感情から抜け出すのが難しくなる。
ただしこれは、資本主義社会が直接欺瞞(詐欺)を働いているわけではなく、個人の選択になっている。
消費者には「買う自由」と「買わない自由」を同等に与えられているのだが、資本主義の構造上「買わない」という選択の先に幸福があるようなマーケティングが存在しないので、インフルエンサーなどの優雅な生活(見せかけ)に感化されると、ずっと消費し続ける事になり、より多くの収入が必要となり、ますます労働から抜け出せなくなる。
これは消費の全てを否定しているのではなく、誰かには買ってもらわないと経済が回らなくなるので、既に現在の状況で満足してる人(つまり、労働により「普通の幸福」がかなえられてる人や、親の初期資産や人脈などの偶然の因子によって高い報酬を得る事ができる人)に、存分に消費していただけばいい。
それによって経済が活性化し、税金も徴収され、ライフラインも充実するのだから、羨む必要も嫉妬する必要もない。
すると「自分はいつ使うのか?」という問題。それは自身が本質的に自由になった暁に、晴れて(自由にできる範囲で)使えばいい。だから事実「資産家に質素な人が多い」のもそれの価値を知っているからなのだろう。
「無知は力」、「ビッグ・ブラザー」は欠乏感を刺激する広告の中にいる
『買わない自由』は存在するのだが、マーケティングは常に新しい商品、より大きな欲望の充足、他人からの羨望の眼差し(つまり「見栄」)こそが幸福への道だと喧伝する。資本主義はその「欠乏感」を埋めるためには消費が必要だと刷り込み、近所が普通に持ってる”それ”を得なければ負け組だと感じてしまい、「貯金ゼロにもかかわらず贅沢品に囲まれた生活」に陥ってしまう。
これが資本主義社会にとって好都合で、ジョージ・オーウェルの『一九八四年』で描かれていた全体主義国家のような直接的な思想統制の必要はなく、自らの自由選択という体裁を取りながら、実際には資本主義の巧妙な仕掛けによって、個人の欲望が際限なく刺激され、自らの意思で巨大な経済の歯車を回し続けるギアに組み込まれていく。
テレスクリーン(スマホ)からは国家の都合のいいプロパガンダの代わりに、よりパーソナライズされた広告やコンテンツが流れる。その結果、それを個人の自由選択だと受容されていく。
この「経済」にとって最も好ましい状態を資本主義は肯定し、労働者はより消費する為に、より長く働くことを「労働の美徳」と内在化してしまう。その画一的な価値観によって、多様性は抑圧され、それを共通規範だと、自発的服従が完成してしまう。
これこそが、まさに資本主義における「ビッグ・ブラザー」であり、主体的な生を奪い去る、最も恐ろしい元凶になっている。
しかし、この巧妙な仕組みにも「買わない自由」、つまり自分にとってそれが本当に必要かを選択する機会(という名のバックドア)が資本主義(民主主義)には用意されている。だから資本主義は詐欺ではないという正当性を保つことができ、それを「個人の自由意志だ」と言い逃れられてしまう。
つまりそれを逆に利用すれば、たとえ「持たざる側」だったとしても、この主体的に行使できる選択により不要な贅沢を慎み、収入の半分、もしくはそれ以上を二桁年間貯金に回すだけで、運や環境に依存することなく、主体性を取り戻すための原資(他者に与えるための原資)が捻出可能になるはずだ。
極限の貧困でなく、少なくとも健康体で外食できる程度の余裕があるならば。
五章:原資の使い道。「投資への飛躍」
「原資」の使い道は、一般的な「投資」だけに限定してるわけではなく、「(他者に)価値を与える」という事だが、とはいえ持たざる側だからこそ「投資」には大きなメリットがある。
それは、持たざる側でも”優遇された人”に資金を投じる(与える側に回る)ことで、自身の家庭では不可能だった高い社会貢献・イノベーション活動の一旦を担う事ができ、その対価として「利益」という形で正当評価を得る事ができるようになるからだ。
更にこれは、経済的な利益だけでなく、精神的な障壁の克服にも高い価値を持っている。つまり彼らが「そもそも優遇された環境ありきで活動できている」のだとしても、優遇者たちも結果的に「優遇された者の中での競争」があり、彼らが行う活動のリスクや努力の先に生み出される価値(経済効果)が高ければ高いほど、こちらにとっても(社会にとっても)有益になるのだから感謝に値すると知る事になり、その結果、優遇されている彼らに対して嫉妬心や劣等感などを抱かなくなる。
これは開き直りではなく端的に言うと、わざわざ不利な状況を背負って自らバッターボックスに立つより、自分より確実にホームランを打つ人に任せた方が効果(価値)が高いという事。なぜならそこには「優遇された者」の中でも競争のすえ勝ち残った「更に優れた者」が立ってくれるのだから。
こう理解すると自身が「(社会が求める)優秀≒ヒーロー」である必要はないという事実もおのずと理解できるようになる。
(経営者や投資家に「資格」が不要という事実がそれを表している。)
この価値提供的思考、行動原理の本質を理解するために、誤解を解いておく必要がある。
「まず与える」というのは綺麗事ではなく、投資に対しても多くの人は自身が儲かる為の行為だと思われてる節があるが、実際には企業(投資先)が儲かる為の仕組みであり、自分が儲かる為の仕組みではない。なので投資もまた社会貢献(愛)であり、これは事実論的にみても経済成功者の行動原理でもある。(ラリーペイジにしても、バフェットにしても)
これが投資の真理であり、「投資家は労働せずに稼ぐのはズルい」といった感情も、その投資の本質的な認識の誤りから発生してるのだと思う。
これに対して、一般的な反論として「投資はリスクを抱えてる」とよく言われるが、それも事実だが、ズルさへの反論としてはまだ本質を捉えきれておらず、ますます誤解を生むように思う。
彼ら投資家の報酬は「労働の対価ではない」だけであり、少なくとも情報収集等、一切労働を行っていないわけではない。
ただ彼らの思考は、そもそも「労働価値説」ではないので、情報収集・分析など、そこに付随して労働が(仮に一日8時間)あったとしても、それは「資本価値の為の補助行為」だと認識しており、彼ら自身は「労働の対価だ」とは思っていないはずだ。
そして、いち早くこの経済の仕組みに気づき先に莫大な資産を持った側が、複利によりますます資産を増やすことができてしまうので、感情的にズルさを感じてしまう原因なのだと思う。
だから、労働にやりがいを感じる事、それに巡り合えたのならそれは素晴らしい事だが、それとは別に、キャッシュフローの源泉がどこなのかをまず理解する必要があるという事。
当然これで誰しも利益が出るわけではないが、とはいえそもそもルールを間違っていては「同じ土俵」にさえ立てないのはどの分野でも明らかであり、このルール認識の重要性を、上述したロバート・キヨサキ著書*『キャッシュフロー・クワドラント』における左側(労働者/個人事業主)が右側(ビジネスオーナー/投資家)になる際の障壁として解説していたのだと思う。
*「労働者が投資家になるのは職業を変えるのではなく価値観そのものを変える必要がある」というような感じで説明されていた。
そしてもう一点、投資には損失のリスクは当然伴う。しかし、そもそも無駄に贅沢していた分から行っているので、その損失はそもそも無いという事もできる。なので、むしろ極論、株価が50%下落しても、まだ半分残ってるともいえる。
更には、この際なのではっきり言うと、(優遇されてその立場にいるはずの)投資先が思うように株価を上げる事が出来なかった場合には、「所詮彼らは家庭環境が優遇されていたからその地位につけただけで、たいして優れてないじゃん(笑)」と心の中で小ばかにしてやればいい。彼らの享受する「普通の幸福」さえも断った不遇側(の行う投資)は、そのくらいの権利は既に得ているのだから。
だからこそ、彼らが優遇された環境だったとしても、起業家もまた競争してるという事実により、実際に株価(というか、特に「営業CF」)*注が上がれば=社会貢献しているという事であり、彼らに感謝の念を感じるようにもなる。
*株価は地政学等に影響を受けて変動するため。
少し話がそれたが、これは投資を斡旋してるわけではなく、つまりお金の本質(ルール)とは「労働の対価」ではなく「社会貢献の対価」であり、それは自らの「労働力(時間・知識・スキル・容姿etcetc)」からでも「資金」からでもどちらでもいいというのが資本主義社会になっている。
そして、トマピケティの資本論で解明していたように、労働による経済成長率より、投資による資本収益率の方が高い(「r>g」)*注という事実がある。
だから、無い側ならばこそ、少しでも多くの原資の獲得し、少しでも早く他者に与える側に回る(=資本を提供する側に回る)というのが、極めて高い価値になる。
経済的自立の再定義
結局は、不労所得による「経済的自由」の話のようになってしまうのだけれど、ただ、その表現をそのまま使うと、流行の「サイドFIRE論」のような、理想を大きく語るだけの再現性のない啓発本などになってしまう。
なので「精神的豊かさ」の獲得の重要性という観点で話を展開してますが、結果的にこの生き方(思考)が、総資産100兆円などという桁違いのウォーレン・バフェットのような本物の資本家が実践する、資本主義の基本構造((r>g)という「経済モデル」)と同じであることは明らかであり、そこに存在する(巨額の)収入の差は、学歴や努力の差ではなく、「初期原資の絶対的な額」と、それを「確保するまでの時間軸」の差だけなのです。
なので、「持たざる側」が「主体的な生」を獲得するためには、感情論を排し、可能な限り早く、可能な限り多い「原資の獲得」に集中することが必要不可欠になっており、その為には、不平等を嘆くのではなく(時間の無駄なので)、不平等構造に加担せず「買わない自由」を行使して、(価値を)与える側に回る。
その結果、「優遇された者」たちへの嫉妬や劣等感は消滅し、彼らを「(不平等に)富を奪う敵」ではなく、「社会に貢献するパートナー」として客観的に評価できるようになり、そこから得た収入(配当)は、たとえ少額でも、自分の主体性が生んだ「社会貢献の対価」だと認識できるようになる。
そして、より大きな影響を社会に与える為には、より大きな資本が必要で、その資本の重要性を知ってるからこそ、バフェットのような「本物の資本家」ほど無駄な贅沢を慎む傾向があるのだと思う。
つまり、資本家(大金持ち)でさえ贅沢を慎むのは、「清貧」といった単なる精神論からではなく、今日の無駄な出費が将来の「より大きな経済的自由の損失(複利の機会損失)」と繋がってると知ってるからだろう。
だから、(持たざる側ならこそ)「贅沢の為」ではなく、まず「最低限の生存の自由(生活)」を確保するために、少しでも多くの資本を積み上げる必要がある、という事。
最終章:不平等な社会を「持たざる側」はどう生きるか
上述を踏まえて、少なくとも私が辿りついた「解」は、、、
一般労働者の家庭に生まれると”より稼ぎがたい”のは、”真面目さ・(学歴的)賢さ”といった能力の差ではなく、「資金がそもそも無い」という現実が、心の余裕を奪い、お金がないことへの不安から、短期的な利益を優先してしまい、短期的な利益を追求するほど「価値提供」から離れてしまい、人に(特にタダでは)与えたくないのに自分だけは欲するから、より「負のスパイラル」に陥ってしまっているように思う。
労働が報われないかどうかは、福利が叶ってるかどうかであり、即ち、必ずしも労働だと報われないわけではなく、福利を取るか自由を取るかは各人の問題になる。
とはいえ、これに漬け込んで、労働者に無理を押し付けてる企業が多くあるのも事実なのだけれど、雇われた側が、貰った給料で私欲を叶えている(恋人とデートしたり、結婚したり、ローンで高価な物を購入したり)という事実がある。
なので得た給料で贅沢をしているにもかかわらず、幸せに感じないのなら、”物質主義”に陥ってしまっている。
冒頭にも述べたように「機会は平等に与えられていない」これは絶対的な事実。自由に学ぶことも難しい「持たざる側」がC卒後に新聞配達とコンビニを掛け持ちし、ブルーの中でも最もハードと言われるビル解体(イカツクはない)まで経験して自力で10段登るより、散々親のスネ(資金)で高校、大学、果てはぬくぬく留学までさせてもらって30段登った「優遇された人」の方が評価されるのは、より高い価値を社会に与えているという事実が評価されるのが現実世界のルールになっているから。
つまり、この「不平等」の根源は、国家が資本主義を採用してる以上、資本の量が生存の優位性を決める最も重要な因子になっており、その結果、先に「持ってる側」が圧倒的に有利なゲーム(社会)になっているからだ。
だからこそ、その社会の不平等に対して、ただ被害者意識を持つのではなく、資本主義の仕組みを客観的に見抜く必要があり、主体的に生きたいと望むのなら、まず不要な贅沢を慎み「買わない自由」を行使して出来る限り多くの「原資」を得て、人に「与える側」に回るしかない。
誤解の無いように言っておくと、前述したように「与える」とは起業や投資に限定してるわけではなく、他者に対して「価値を与える」という事。
だから、持たざる側でも「労働(による福利)」で幸福が得られれば何よりなのだけれど、そうでない場合、(社会一般が認める)ちゃんと働いてるにもかかわらず報われない感覚が「労働疎外」の原因になっており、その「虚しさや欠乏感」を埋めるために一時的な満足感を得られる消費に走ってしまい、自発的に消費社会に組み込まれて、より搾取されるという構造的不平等に加担してしまうという矛盾を招いてしまう。
なので「持たざる側」が本質的な幸福を得るためには、労働の質を「生活の為(お金の為)」から「自己の尊厳の為」へとシフトさせる事が重要で、その具体的方法は、労働であれ、自営であれ、投資であれ、自分が儲かる為ではなく、他者に(価値を)与える事で報酬を得る。そこからは感謝が発生し、自尊心も得る事ができる。それがセネカの言う「真に生きる生き方」であり、マルクスの指摘した「労働疎外」も解消できるようになる。
つまり「他者に与える」というマインドセット(尊厳・主体性)と、経済戦略(資本原理の理解)は不可分な関係であり、どちらが欠けても成立しないので、先に持ってる側(優遇側)が経済的にも精神的にも有利な社会になっていて、これに囚われ続けることが不遇側が「より負のスパイラル」に陥ってしまう元凶になっている。
なので、結果的に与える側に回る(=価値提供)は偽善でも単なる精神論でもなく、規模は小さくとも本質的には「資本家と同じ道」であり、「自己の尊厳を持って主体的に生きる」という精神的豊かさと、「お金の為に働かなくていい」という経済的な豊かさの「どちらも得られる」(資本次第)という、これこそが社会の欺瞞や不平等から(持たざる側でも)脱却できる資本主義(というか民主主義)が用意した唯一の方法(バックドア)だ。という「解」に至ったという事です。
あとがき
長々語ってきたけれども、この話の最も厄介な点は、この真意を伝えるために強めに社会批判せざるを得ず、結果的に一般的社会価値基準である「労働(や学歴)の美徳を完全否定してるように見える」という点。
これは長年慣れ親しんだ「労働」という(お金を得るための)手段と、「努力の正当性」という価値観・美徳が、経済システム(資本の事実)と真正面から衝突してしまうからであり、なので上記したロバート・キヨサキの提唱する「キャッシュフロー・クワドラント」も(特に個人の努力を美徳とする風習の根強い日本において)賛否の原因*注の一つとなっているのだと思う。けれども、キヨサキ氏自身も経済の真実を説明しているだけで、労働自体を(そこで従事する人を)否定しているわけではないのだと思います。*これの美味しい所だけを利用して「労働しなくても稼げる」などと謳う一部の怪しいセ〇ナーやマ〇チの勧誘に利用されたりするのも原因だと思う。
この事について私の見解・主張も付け加えさえてもらうと、このブログを始めた原点でもある「肉体労働では幸せになれない理由(別ページ)」でも触れてるように、非常に過酷で辛い仕事でしたが、どうあれ結果的に「社会価値に繋がってる」という事実も分かってるので、学問を修め、高度な知識や技術で重要なポストに就き、社会を支えている方々も、もちろん立派な「社会貢献」であり、労働(つまり一般的なサラリーマン)という生き方も、資本主義の欺瞞に遭う事もなく、普通に生きて「平凡という最高に幸福な人生」を得られれば何よりだし、労働は社会貢献ではないと言ってるわけではないという事を補足させていただきます。
ただ、再三述べてきたように、父は会社の過度な売り上げ要求に、恐らく不渡りか何かを出したのか、その損失の責任を父に押し付け、自主退職という体裁を取り、はっきり言って強制退職を余儀なくされ、その際支払われる退職金を「損失のかた」として全て没収された挙句、その後大病を患い、当然そもそも裕福な家庭ではないので、預金など殆どないうえに、上述の通り退職金さえも取られてしまっているので入院費が足りず、父が亡くなるまでの数年間、その不足分を私も一緒になってサポートする事になり、それが直接嫌だったというわけではないのですが、とはいえそういう所で優遇側との「機会の差」が広がるのは事実ですが、話がそれるので割愛…
少なくとも「現社会の労働はほんの些細なミスや不運で簡単に崩れる。」という事を実感し、報われると保証されていない「労働」を辞めようと思うに至りました。
その父の件が最終的なトリガーにはなってますが、そもそも幼少期からの素朴な疑問として、「なぜ課長や部長という肩書の人は一つの仕事で時間いっぱいいっぱいなのに、それより偉い=忙しい(はず)の取締役なんて人がいくつもの会社の役職(肩書)を持てるのだろうか?」という違和感がありました。
それが、後に私が直面した父の件と結びつき、「資本のルール」を見極めなければならないという確信に繋がったように思います。
その為に、酒たばこギャンブルのような娯楽(←これにはそもそも余り興味がないのが功を奏した)は勿論の事、借金(ローン)はすべて返済し、果ては結婚(に付随する恋愛)といった普通にしてれば普通に享受できるような全てをXX年間犠牲にして、最低限の原資を得て、今でも食費は100円~200円程度を前提にしたり、という方法でようやくこれ(主体的に生きる)を成立させてるという感じです。
その結果、私自身の手で出来る価値提供として、私の場合ブログで数年間(出来る範囲で)情報提供してきた結果、今では月平均1万PV*注にまでなり、大した収入ではないですが←重要、企業からお問い合わせが来たり、極稀ですが読者から感謝のメールが来ることもあったり、この「他者に価値を与える」が机上や綺麗ごとではなく、現実世界でも機能している証拠だと実感しています。(*これは全サイト運営者の5%~10%の割合らしい。)
その他に、四季報を参考に企業投資も行い、利益も得ていたりしますが、超少額←再度、これも結局は自分の為でもあるけれど、まず先立ってるのは「他者に与える」という行為・認識であって、それが優遇者(成功者)との差からくる劣等感や嫉妬からも解放されて、結果的に自分にも返ってくるという、好循環になっていくのだと考えてます。
なんだか、極度の貧困家庭から抜け出すサクセスストーリーのようにも見えてしまうけれど、確かに、両親はかなりの貧困家庭だったのは事実で、その影響で私自身も自分の興味で学びたい事を選択できるほど裕福な家庭では無かったので、上述したように中卒で新聞配達したり、(小柄で)重労働のビル解体なども経験したのも事実ですが、
とはいえ、父は(文字通り)命を賭して労働に尽くした結果、徐々に収入が増えて、ぼろ屋ながらも持ち家を得る事はできたので、私自身は両親のような「極度の貧困家庭というわけではなかった」という事を誤解の無いようはっきりさせておこうと思います。
なのでこの主張・方法は「日々の生活でいっぱいいっぱいだ」という方々には対応してないし、これでも選択できるだけまだ贅沢・幸福だという事も承知してますので、当然これが誰にでも当てはまる(実行できる)とは全く思っていませんし、それまでの代償がでかい事も分かっているので、これはあくまで、私自身の「個人的な選択」だとご理解いただければと思います。
編集歴:201128 201215 201224 210313 210124 210609 210718 211030 220413 220727 230130 2401 2405 2410 2412 2501 2505 2508再構成 2509 2510 2511あとがき追加 2512微調整 251220最終調整(完)2601微補足編集 全ての編集において大きな内容の変更は伴わない。